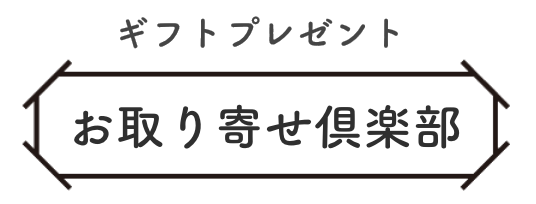お中元と喪中のマナー完全ガイド:贈り方・受け取り方のポイントを詳しく解説
2025年06月19日更新
大切な方が亡くなられた後、お中元の時期を迎えて悩まれている方も多いのではないでしょうか。
喪中だからといってお中元を控えるべきなのか、贈る場合はどんな配慮が必要なのか。
心配や戸惑いは尽きません。
実は、お中元は感謝の気持ちを伝える贈り物なので、喪中でも適切な配慮があれば贈ることができます。
この記事では、喪中時のお中元に関する基本マナーから実践的なポイントまで、詳しく解説します。
喪中とお中元の基本マナーを理解しよう
お中元は日頃の感謝を伝える夏の贈り物であり、お祝い事には該当しません。
喪中の場合は特別な配慮が必要ですが、贈答することは可能です。
喪中は近親者が亡くなってから慎ましく過ごす期間で、父母の場合は12〜13ヶ月、子どもや祖父母の場合は3〜6ヶ月、兄弟姉妹の場合は30日〜3ヶ月を目安とします。
また忌中期間は特に重要で、仏教では四十九日、神道では五十日の間、遺族は身を清める時期となるため、香典返しなどの贈り物を控えるのが一般的です。
相手の宗教や宗派によって異なる場合もあるため、事前の確認をおすすめします。
お中元の基本マナーとしては、地域によって7〜8月の時期に贈ること、紅白の蝶結びののし紙を使用すること、食品や日用品など消えものを選ぶことが挙げられます。
縁起が悪いとされるものや不幸を連想させる品物は避け、実用的なものを贈りましょう。
喪中期間中にお中元を贈っても大丈夫?
喪中期間中のお中元は、日頃の感謝を表す目的であれば贈ることができます。
ただし、故人を偲ぶ大切な期間であることを考慮し、以下の点に気を配りましょう。
- 忌中期間(仏教:四十九日、神道:五十日)は控える
- のし紙は白無地や短冊のしを使用し、華やかさを抑える
- 表書きは「御供」「御伺い」など配慮ある表現を検討
- 高額な品物は避け、食品や日用品など消えものを選ぶ
- 紅白などの華やかな包装は避け、シンプルに
- お悔やみの言葉を添え、相手の心情に配慮
- 時期をずらし、暑中見舞いや残暑見舞いとすることも検討
相手の状況や気持ちを第一に考え、慎重に判断することが大切です。
自分が喪中の場合:お中元を贈る際のポイント
喪中であっても、感謝の気持ちを伝えるお中元は贈れますが、忌中期間中は控えることをおすすめします。
贈る際の表書きは「御中元」で問題ありませんが、必要に応じて「粗供養」や「御供」を選択し、白無地の奉書紙や短冊のしを使用します。
相手に負担をかけないよう、高価な品物は避け、食品や飲料など消えものを選びましょう。
挨拶状には喪中である旨と丁寧なお詫びの言葉を添えることで、相手への配慮を示せます。
また、時期をずらして暑中見舞いや残暑見舞いとして贈るのも一つの方法です。
自分が喪中のときにお中元を受け取った場合の対応
喪中でもお中元を受け取ることに問題はありません。
お礼状には、喪中である旨と、相手のお気遣いへの感謝の言葉を添えてください。
喪中であることを相手が知らなかった場合、故人のことには具体的に触れず、感謝の気持ちを中心に伝えましょう。
お返しは必須ではありませんが、贈る場合は消えものを選び、相手に負担をかけない配慮が必要です。
暑中見舞いや残暑見舞いの時期に合わせることで、自然な形で感謝の気持ちを伝えられます。
相手が喪中の場合:気をつけたいマナー
相手が喪中の場合は、特に慎重な対応が求められます。
忌中期間中は贈り物を控え、忌明け後に贈りましょう。
時期が重なる場合は、暑中見舞いや残暑見舞いとして贈ることも検討できます。
宗派による忌明けの違いにも注意が必要で、迷った際は、お悔やみの挨拶や電話での確認が望ましいです。
品物選びは特に重要で、縁起が悪いとされるもの(櫛、刃物、ハンカチなど)や不幸を連想させるもの(お茶、海苔など)は避け、実用的な日用品や食品を選びましょう。
また、のし紙や包装も華やかさを抑えた上品なものを選択することも大切です。
喪中の相手からお中元を受け取った場合の対応
喪中の方からお中元を受け取った際は、相手の気持ちに寄り添った対応が重要です。
故人のことには具体的に触れず、お気遣いへの感謝の気持ちを丁寧に伝え、お返しをする場合は、相手の喪中期間を考慮した時期と品物を選びます。
特に忌中期間中は、お返しを控えるか時期をずらすなどの配慮が大切です。
お礼状では、相手の心情に配慮した温かみのある文面で、日頃のご厚誼への感謝の気持ちを伝えます。
なお、相手が喪中であることを知らずにお中元を贈ってしまった場合は、改めてお悔やみとともにお詫びの言葉を添えましょう。
実例でわかる:喪中に送るお中元・残暑見舞いのタイミング
お中元は忌明けを待ってから、通常の贈答時期に合わせて贈ります。
忌中期間が終わっていない場合は、8月中旬以降に残暑見舞いとして贈るのがよいでしょう。
地域によって一般的な贈答時期が異なり、関東では7月1日〜15日、関西では7月15日〜8月15日が目安です。
準備は2週間前から始め、相手の法要などの予定も考慮し、お届け希望日の5日前までに注文することをおすすめします。
オンラインで注文する場合は配送時間帯も指定できるため、相手の生活リズムに合わせた贈り物が可能です。
喪中時にお中元を控えるケースと代替案
忌中期間(故人が亡くなってから49日まで)は、お中元を控えるのがマナーです。
この期間後に、残暑見舞いやカジュアルな『夏の贈り物』として贈ることをおすすめします。
喪中の方は贈り物を辞退される可能性もあるため、事前に確認しましょう。
代替案として、「サマーギフト」という表現を使ったり、記念日や誕生日に合わせて贈ったりする方法もあります。
日頃の感謝を伝える手紙を添えることで、より丁寧な気持ちを届けられます。
職場の方への贈り物の場合は、部署全体への贈り物として検討するのも一案です。
喪中時の表書き・のし紙・熨斗の選び方
喪中時の贈り物には、白黒、双銀、または黄白の水引を使います。
表書きは「御中元」「暑中御見舞」「残暑御見舞」から選び、印刷された熨斗は避け、白無地の奉書紙や短冊を使用します。
薄墨での表書きも喪中時の配慮を示すひとつの方法で、オンラインショップでは専用オプションが用意されており、注文時に指定できます。
贈り主の名前は楷書で丁寧に記入し、肩書きがある場合は適切に記載するのも大切です。
喪中における具体的な熨斗・包装マナー
熨斗は結び切りを選び、蝶結びは避けます。
包装は特別な指定がない限り通常の包装紙で問題ありませんが、華やかな柄は避けましょう。
表書きの下には必ずフルネームを記入し、連名の場合は個別に贈るのが望ましいです。
最近は簡易包装の選択も増えていますが、熨斗や表書き、品物の梱包には十分な配慮が必要です。
贈り物を手渡しする場合は、包装紙の上からさらに風呂敷で包むなど、より丁寧な印象を心がけましょう。
避けたい品物と選び方のポイント
喪中時は、故人の好物だった品や香典返しと似た品物、生鮮食品は避け、慶事用の紅白の水引・のし紙が付いた商品も控えましょう。
お菓子・飲料・調味料などの日持ちする品や実用的な日用品が適しています。
カタログギフトも、相手の好みに合わせられる選択肢として人気があります。
最近は健康志向の商品や環境に配慮したエシカルな商品も注目されており、オーガニック食品や自然素材を使用した日用品は、相手への気遣いを表現できる贈り物です。
また、防災用品やヘルスケア商品など、実用性の高い品物も検討価値があります。
商品の価格帯は、普段のお付き合いの程度を考慮して決めましょう。
喪中のお中元最新事情:オンラインギフト活用術
近年は、熨斗や包装の指定、配送日時の調整も簡単にできるオンラインギフトサービスの利用が広がっています。
喪中時は特に、カタログギフトやeギフトなど、相手に気を遣わせない形式が重宝されます。
豊富な品揃えから24時間注文可能な便利さが特徴で、デジタルギフトカードやオンラインクーポン、サブスクリプション形式のギフトなど、新しい形態の贈り物も登場。
スマートフォンアプリを使えば、贈り物の選定から決済、配送状況の確認まで一括管理が可能です。
また、ギフトの履歴管理機能を使えば、次回の贈り物選びにも役立ちます。
喪中期間にお中元を贈る・受け取る際のQ&A
【贈る側の疑問と対応】
Q1:いつから贈っても良いですか?
A:忌中期間(49日)が明けてからが基本です。
- 具体的な対応
- 忌明け直後なら残暑見舞いとして贈る
- 地域の慣習も考慮して時期を選ぶ
- 早めに贈る場合は事前確認を
Q2:熨斗と包装の選び方は?
A:華やかさを抑えた、シンプルな形式を選びます。
- 選ぶべきもの
- 水引:白黒、双銀、または黄白
- 熨斗:結び切り
- 表書き:白無地の奉書紙か短冊
- 包装:通常の包装紙(華やかな柄は避ける)
【受け取る側の対応】
Q3:故人宛のお中元が届いたら?
A:以下の手順で丁寧に対応します。
- お礼状の作成
- 訃報が届いていなかったことのお詫び
- 今後の送付先の変更依頼
- ご家族で相談の上、品物の取り扱いを決定
Q4:お返しや御礼はどうする?
A:喪中でも感謝の気持ちは適切に伝えましょう。
- 基本マナー
- 品物のお返しは不要
- 気持ちだけお受け取りする旨を伝える
- お礼状は必ず送る(受け取り後1週間以内)
- お礼状の書き方・送り方
- 手書きが基本
- 白または薄いグレーの便箋に白無地の封筒、もしくは喪中はがきを使用
- 時候の挨拶から始める
- お祝いの言葉は使わない
- 近況報告を含める
- 感謝の言葉で締めくくる
- 郵送は速達
【トラブル対応】
Q5:受け取りを辞退したい場合は?
- 望ましい対応
- 事前に周囲への意向伝達
- 丁寧な説明と感謝の意を示す
- 代替の時期の提案
- お心遣いへのお礼状送付
まとめ
お中元は喪中の場合も、以下の4つのポイントを押さえることで、贈答が可能です。
- お中元は感謝の贈り物であり、お祝い事ではないため、忌中期間を避けて贈れる
- 食品や日用品など実用的な消えものを選び、故人の好物や不幸を連想させるものは避ける
- のし紙や包装は華やかさを抑え、白無地や短冊のしを使用する(オンラインでも専用オプションが利用可能)
- 地域の慣習を考慮し、必要に応じて暑中見舞いや残暑見舞いとしての贈り方も検討する
この記事を参考に、最適な贈り方を見つけていただければ幸いです。